Feynmanダイアグラムを描いてみた(自由粒子のFeynman核) ーPart4ー
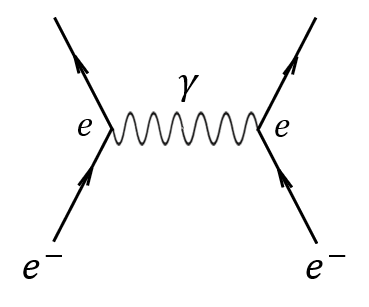
$$\def\bra#1{\mathinner{\left\langle{#1}\right|}}$$ $$\def\ket#1{\mathinner{\left|{#1}\right\rangle}}$$ $$\def\braket#1#2{\mathinner{\left\langle{#1}\middle|#2\right\rangle}}$$
☆前回までのキーワード:Feynman核 Euclid化 Euclid-Feynman核
前回はFeynman核のEuclid化を導入、Euclid-Feynman核が有効な量であることを見た。今回はこれらの量をより具体的なケースで計算してみる。
まずは自由粒子の場合を簡単のために1次元で考える。この場合のHamiltonianは$$\hat{H}=\frac{1}{2m}\hat{P}^2$$で与えられるからこれをFeynman核の中の位相部分に入れてあげればいい。実際には初期時刻\(t_0=0\)として時刻\(T\)でのFeynman核は$$K(x,x_0;T)=\bra{x}exp\left(-\frac{iT}{2m\hbar}\hat{P}^2\right)\ket{x_0}$$となる。ここからどのように進めるかだが、運動量演算子が入っているので運動量の完全系を挿入してあげることでこれはc-数(演算子でない普通の数)に置き換えることができる。$$\begin{align}K(x,x_0;T)&=\int_{-\infty}^{+\infty}dp\bra{x}exp\left(-\frac{iT}{2m\hbar}\hat{P}^2\right)\ket{p}\braket{p}{x_0}\\ &=\int_{-\infty}^{+\infty}dp exp\left(-\frac{iTp^2}{2m\hbar}\right)\braket{x}{p}\braket{p}{x_0}\end{align}$$次に後ろについている2つのbraketを計算したいが、これは簡単に求まる。まず運動量演算子の行列要素\(\bra{x}\hat{P}\ket{p}\)を考えることから始まるがこれは2通りにみることができる。1つ目は\(\hat{P}\)が\(\ket{p}\)に作用してc-数\(p\)に置き換わるというのと、2つ目は\(\hat{P}\)が\(\bra{x}\)に作用して微分演算子\(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\)に置き換わるというものである。両者は当然等式で結ばれるので$$\frac{\partial}{\partial x}\braket{x}{p}=\frac{i}{\hbar}p\braket{x}{p}$$となり、結局\(\braket{x}{p}\)を求めるためにはこの微分方程式を解けば良いと言うことになる。この解は$$\braket{x}{p}=Cexp\left(\frac{i}{\hbar}px\right)\quad(C: Const.)$$とすぐに求められる。定数は座標の直交性と運動量の完全性を組み合わせることで$$\begin{align}\delta(x-x’)=\braket{x}{x’}&=\int dp \braket{x}{p}\braket{p}{x’}\\ &=|C|^2\int dp exp\left(\frac{i}{\hbar}p(x-x’)\right)\\ &=\hbar|C|^2\int dp e^{(ip(x-x’))}\\ &=2\pi\hbar|C|^2\delta(x-x’)\end{align}$$とできるので結果$$C=\sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}}\quad (C>0)$$と決まる。よって本来求めたかったbraketは$$\braket{x}{p}=\sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}}exp\left(\frac{i}{\hbar}px\right)$$となる。これを踏まえてFeynman核の計算に戻ると$$K(x,x_0;T)=\frac{1}{2\pi\hbar}\int dp exp\left(-\frac{iT}{2m\hbar}p^2\right)exp\left(\frac{i}{\hbar}p(x-x_0)\right)$$これで運動量積分を実行できるexplicitな形に持ってくることができた。これを単純なGauss積分に持っていくためには位相部分で\(p\)に関して平方完成をすればよい。結果としては\begin{align}K(x,x_0;T)&=\frac{1}{2\pi\hbar}exp\left(\frac{im(x-x_0)^2}{2\hbar T}\right)\int dp exp\left(-\frac{iT}{2m\hbar}\left(p-\frac{m(x-x_0)}{T}\right)^2\right)\\ &=\frac{1}{2\pi\hbar}exp\left(\frac{im(x-x_0)^2}{2\hbar T}\right)\int dp exp\left(-\frac{iT}{2m\hbar}p^2\right)\\ &=\frac{1}{2\pi\hbar}exp\left(\frac{im(x-x_0)^2}{2\hbar T}\right)\sqrt{\frac{2m\hbar\pi}{iT}}\\ &=\sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar iT}}exp\left(\frac{im(x-x_0)^2}{2\hbar T}\right)\tag{1}\end{align}となってこれが最終的な答えである。
最後にこの計算結果が確かにFeynman核の初期条件を満たしていることを確認しよう。そのためには\(T\to 0\)の極限のもとで(1)式が\(\delta\)関数になっていればよい(Feynman核の満たすべき初期条件は\(K(x,x_0;t_0,t_0)=\delta(x-x_0)\)。詳しくは前のPartを参照)。極限をとると$$\lim_{T \to 0}\sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar T}}exp\left(-\frac{m(x-x_0)^2}{2i\hbar T}\right)$$であるが、これと\(\delta\)関数の定義式を見比べると$$\delta(x-x_0)\equiv\lim_{\epsilon\to 0}\frac{1}{\sqrt{\pi\epsilon}}exp\left(-\frac{(x-x_0)^2}{\epsilon}\right)$$これらは\(\epsilon\to\frac{2i\hbar T}{m}\)の置き換えの下で等しいことがわかる。ちなみに\(\delta\)関数の定義にはよくFourier変換(1をFourier変換すると\(\delta\)関数になる)が有名だがこの表式はGaussianの幅を\(0\)にとる極限で\(\delta\)関数を定義している。とは言っても(1)式に対してこのような極限をとっても結局は振動してしまうためこの対応が本当かどうか疑わしい。そこで(1)式に\(x\)積分を実行すると確かに\(1\)になりこれが\(\delta\)関数であることが保証された。
今日はここまで。自由粒子とは言えどこれで記事1つになってしまった…
次回は自由粒子の場合のn点関数を計算する。
本ブログは神様を信じている学生の物理ブログです。ぜひ他の記事も見てみてください(^^)
投稿者プロフィール

-
素粒子物理学を研究しています。
物理学を「面白い学問」で終わらせないこと、そこから「人生のなかで核心となる精神」を学んで生きることが僕の哲学です。
最新の投稿
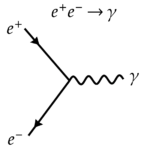 日々思うこと2021年3月17日鄭 明析牧師の名説教:「愛の電気」
日々思うこと2021年3月17日鄭 明析牧師の名説教:「愛の電気」 日々思うこと2021年2月21日しばらくM1 mac book proを使ってみて思ったこと
日々思うこと2021年2月21日しばらくM1 mac book proを使ってみて思ったこと 日々思うこと2021年2月20日「対称性の破れ」からみる神様の性格
日々思うこと2021年2月20日「対称性の破れ」からみる神様の性格 日々思うこと2020年8月31日光のDoppler効果 ー高校生のときの思い出ー
日々思うこと2020年8月31日光のDoppler効果 ー高校生のときの思い出ー

